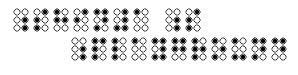掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第257号,2021年8月.
「実践の糧」vol. 60
室田信一(むろた しんいち)
先日、障害者にかかわる日本の制度改革や障害者の社会参加を促進することを目的に活動してきているDPI日本会議という団体の副議長の尾上浩二さんのお話を伺う機会があった。尾上さんがこれまでに関わられてきた様々な取り組みには、大阪の地下鉄のエレベーター設置を要求する活動や、自立生活センターの立ち上げ、障害者自立支援法制定反対行動などがある。それらの取り組みはどれも重要な活動で、活動の舞台裏も含めてお話を聞くことができたことは大変勉強になった。しかし、私が最も感動したことは、尾上さんがご自身の経験してきたことや、その当時の状況などを説明する際の語り方であった。
尾上さんは過去にご自身が取り組んできたことを大袈裟に話したりドラマチックに話したりすることはなく、それでいて事実だけを伝える冷たい話し方でもなく、内に秘めた情熱に支えられた真摯な実践を丁寧な言葉で表現してくださった。実践の現場では、厳しい現実について語ることで共感を得ようとすることや、希望的な観測を示すことで支持を得ようとすることが効果的な語り方として用いられることもあるが、そうした表面的な語りのテクニックは全く見られなかった。尾上さんの語り方からは、したたかな現状分析に基づく実直な実践を積み重ねてきたことがよくわかったし、だからこそ現実社会に確実に変化を与えてきたことが確認できた。その眼差しの先にさらなる変化を求めていることが伝わったが、かといって野心のようなものを感じることはなく、日々の実践の先に変化を生み出していくことへの覚悟のようなものを感じ取ることができた。
尾上さんの話を伺っていると、私がアメリカで出会ったコミュニティ・オーガナイザーたちの姿が思い出された。私がかつて住んでいたアメリカのニューヨーク市には、コミュニティが直面しているさまざまな生活上の課題や人権の問題など、個人では変化を起こすことができない状況に対して、コミュニティが連帯して働きかけられるように、そのコミュニティに関与するコミュニティ・オーガナイザーたちがたくさんいた。「社会を変える」というとマスメディアで取り上げられるような世間の注目を集める大きなキャンペーンが想像されるかもしれないが、実際は名もなきオーガナイザーたちが、コミュニティの中で住民と対話を繰り返し、作戦を練り、変化を求めて各方面に貪欲に働きかけている。
私もかつてはそうした姿勢を大切にしていたはずなのに、いつからか変わってしまったように思う。具体的な変化が日々生み出される実践の現場に対して、私が今いる場所は具体的には何の変化も生み出すことをしていない。現実を可視化して記述したり、分析して説明したり、もしくは批判的に検討したりすることが研究者としての役割であると自認しているが、具体的な変化とは程遠いところにいるように感じる。研究者には研究者の役割があると開き直ることもできるが、今書いているこの文章も含めて、虚構を生み出している行為にすぎないと感じている。
以前この連載で『サピエンス全史』を取り上げて述べたように、人間社会とは虚構によって成り立っているものだと、自分の行為を肯定することもできるが、やはり実践に裏付けられた言葉の重要性について、虚構と批判されたとしても、これからも悩み続けていきたいと覚悟を新たにした。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。