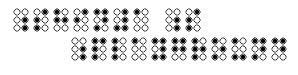掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第241号,2018年12月.
「実践の糧」vol. 44
室田信一(むろた しんいち)
最近、たまたま知った女性4人組のガールズバンドCHAIの音楽にハマっている。ラジオで紹介されていたことがきっかけで好きになったが、最初はその音楽性よりもCHAIが提供する価値観に魅了された。CHAIのメンバーは自分たちのことを「NEOかわいい」と表現している。彼女たちは自分たちの容姿にコンプレックスを抱き、いわゆる世間一般でいうところの「かわいい」カテゴリーに自分たちが該当しないと自覚している。しかし、彼女たちは「すべてのコンプレックスはアート」と宣言し、自分たちを「かわいい」ではなく「NEOかわいい」として捉え、概念の刷新を提案している。代表曲の「N.E.O.」はまさしくその概念を表現した楽曲で、CHAIの楽曲はどれも既存の概念を刷新し、新たな視点を提示するものが多い。自分たちの個性を自由に表現する彼女たちの姿はとても魅力的で、私は楽曲を通して彼女たちが表現する世界観に魅了されるようになり、「NEOかわいい」の虜になってしまった。
私がもっとも共感した点は、「NEOかわいい」ことは「かわいい」ことに対立するものではないということである。つまり既存の概念の否定の上に成り立つものではない。実際、彼女たちは「かわいい」ものが大好きなのである。社会の中には「かわいい」のヒエラルキー構造が存在する。偏った表象によってのみ形成されているそのヒエラルキー構造を否定することは簡単であるが、その構造が成立する世界では「否定すること」は何の効力ももたない。彼女たちは、むしろその構造の存在を認め、構造を理解し、さらには自分たちがそのヒエラルキー構造の上位に位置しないことを自覚した上で、ヒエラルキーの中に存在するゲームのルールを少し変えるということを提案している。それはまるでヒエラルキーというピラミッドの頂点をくるっと回転させて、どの頂点が上部に位置するのかわからなくなるような転換である。
そのような転換は、ブラジルの教育実践家であるパウロ・フレイレが提唱していた意識化や文化行動と共通する。ブラジル社会の中で底辺に位置付けられていた農民たちに対して、フレイレは識字教育を通して彼らが直面している現実世界を理解することを促した。彼らを抑圧する者に対抗し、抑圧し返すことは、結局同じ抑圧的な構造を生み出すこと(=非人間的なこと)であり、それは問題の根本的な解決にはならない。フレイレの教授法は、農民たちが内発的な力を発揮することによって、自分たちがおかれた状況を転換し、彼らが属する社会に反映させるというものである。CHAIのメンバーが自分たちの中に潜在していた「NEOかわいい」側面を表現して、社会に存在する「かわいい」のヒエラルキー構造を転換していることと、共通する部分がある。
私たちの社会には様々なヒエラルキー構造がある。「経済力」はもちろん、「学力」、「身体能力」といったモノサシによって生み出される構造は、その社会を構成するメンバーが受け入れることで成り立っている。その構造は固定化された価値観を強要し、底辺にいる者はもちろん、上層部にいる者にとっても変えることが困難になる。
CHAIの音楽が示す世界観は、いかにして既存のパラダイムを転換するのか、そのヒントと勇気を与えてくれる。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。