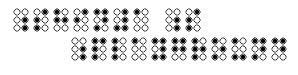掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第211号,2013年12月.
「実践の糧」vol. 14
室田信一(むろた しんいち)
私の母校であるニューヨーク市立大学ハンター校の大学院で受けたコミュニティ・オーガナイジングの授業は今でも忘れられない。授業を担当していたバーグハート先生は、パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』をテキストとして用い、1学期中ずっとこの本の内容についてディスカッションをするというスタイルで授業を進めた。
ご存知の人も多いと思うが、フレイレはブラジル出身の教育者で、貧しい農村における識字教育をとおして農民のエンパワメントを進めたことで有名である。言葉の読み書きができない農民たちに読み書きを教え、言葉の理解をとおして彼らがおかれた境遇の理解を促し、さらに彼らがより広い社会の中に自らの生活を位置づけることを支える。そして彼らが自分たちの生活を変えるために自ら行動をとれるように支援する。そうした一連の過程をフレイレは「意識化」と呼び、そうした考え方はこんにちエンパワメント概念の中核として位置づけられることが少なくない。
バーグハート先生は、学生との対話をとおしてフレイレの思想を教えていた。対話というのは、すなわちフレイレの考え方(意識化)に基づくものである。したがって、学生一人一人は自分という存在を社会との関係で捉え直す作業を求められ、自分にとって、社会にとって、望ましい変革を起こすために具体的な行動をとる必要性と正面から向き合う。そのような授業であるため、時には議論が紛糾することもあった。また、過去には学生の主体的な学びを促すあまり、行動がエスカレートして学生が授業をボイコットするということもあったという。ちなみにその学年では、学生の主体的な行動と決定を尊重し、バーグハート先生が授業に出ないで、学生たちが自ら授業を進めたという。
社会福祉の実践は歴史的に慈善の流れを受けている側面があり、こんにちでも教科書等で述べられる社会福祉には「施し」としての実践という側面が少なくないように思う。また、世の中の理解や社会福祉を専攻する学生の理解として、「福祉=人を助ける」という捉え方が根強く残っている。確かに、個人を支援するという一場面を切り取ってみれば、それは人を助ける行為である。また、支援なくして生きることが難しい人もたくさんいる。しかし、その「助ける行為」をとおして「助けを必要とする環境」を維持してしまっているとしたら、それは社会の中で不利な立場におかれている人がいるという状況を肯定することにもなりかねない。
社会福祉の現場では、現状維持が最善の策という状況は多々あり、それ自体を否定するつもりはない。しかし、当事者が社会の中に自らを位置づけ、自分たちがおかれた状況を少しでも変えたいと考え、行動をとろうとした時、支援者はそのための資源でなければならない。支援者は、当事者の生活を支えるという面では「エンジェル」かもしれないが、社会全体を当事者にとって生活しやすいものに変えたくてうずうずしているという面においては同志である。「たすけあいの会」の「たすけあい」にはそのような意味も含まれているのかもしれない。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。