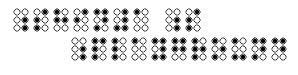掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第232号,2017年6月.
「実践の糧」vol. 35
室田信一(むろた しんいち)
地域包括ケア政策が各地で推進され、行政や社協などが中心となり、住民を地域のサービスの担い手として養成する事業に取り組んでいる。私もそうした事業の推進をアドバイスする立場でいくつかの自治体に関わっている。
そうした事業を推進するための会議に出席して思うことは、自分が理想と思う地域の助け合いのイメージと政府が模索している地域の助け合いのイメージがあまりにもかけ離れていることである。その結果、私が想定する助け合いのイメージを現場の担当者(主に行政の職員)と共有することが難しく、「政府のイメージさえなければ」というような被害妄想さえ抱いてしまう。
地域づくりをする上で実際に手を動かすのは私ではない。そのため、アドバイザーという立場であっても私の描く理想像を現場の担当者に押し付けることはしない。むしろ、担当者が頭の中で描いている絵を引き出すお手伝いをして、その絵が本当に理想の地域像なのか議論する中で、徐々に私の思い描いている絵と重なり合うようになればいいと思っている。
いや、正確には、思っていた。最近その考えが少し変化してきた。
というのも、昨今の政府の政策は、地域活動や住民活動に対して一方的に推進方法を押し付けてきていて、その負の影響力を軽視することができなくなったからだ。
ハバーマスという哲学者が「システムによる生活世界の植民地化」とかつて述べていたが、近年の地域包括ケア政策は草の根の住民活動を植民地化しようとしている。
そうした傾向は今に始まった事ではない。日本では1960年代からコミュニティ政策が推進されてきており、人工的にコミュニティが作られてきた。アメリカでは公民権運動を契機に連邦政府が貧困地域におけるコミュニティづくりに政策的に関与するようになり、コミュニティ・オーガナイザーの配置に予算を充てた。そこで重視されていたことは住民による自治である。そのため、住民がどのような活動に取り組むかということは住民側に委ねられていた。住民が考える課題やニーズに対して、オーガナイザーが中心となり、自分たちで取り組む課題を決めていた。
日本のコミュニティ政策にも同様の傾向はあったのではないだろうか。コミュニティの中に意思決定機関を設置して、住民が中心となってその機関を動かす。しかし、そうしてできた機関が時間の流れとともに機能しなくなることがある。地域に課題があっても特に何も行動を起こさないこともある。そこで、地域住民が取り組むべき課題を政府が地域包括ケア政策によって示し、各地の住民は、右へならえで地域の支え合い活動に取り組むようになっている。
そのような歴史的な背景があったので、地域包括ケア政策もある程度は必要と思っていたが、現在の現場の状況を見ると、早いうちに手を打たなければならないと思い始めている。それも私の夢想なのだろうか。この連載を通してもう少し考えていきたい。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。