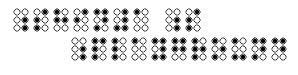掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第224号,2016年2月.
「実践の糧」vol. 27
室田信一(むろた しんいち)
私はしばしば、コミュニティを組織することを演劇の舞台に例えて表現する。演者がその舞台に馴染み、生き生きとその演目を演じることと、コミュニティの中でワーカーが当事者や住民を組織して、彼(女)らが声を発するための場を設定することには、多くの共通点がある。そうした解釈は、前回紹介した『黒子読本』のように、コミュニティワーカーを「黒子」として捉えることにも通じるかもしれない。しかし、前回も述べたように、頭巾で顔を隠して、自身を表に出さない黒子像は刷新される必要があると、私は考える。
アウグスト・ボアールというブラジルの演劇活動家がいる。『被抑圧者の演劇』の著者であり、その演劇の実践を広く普及したことでも知られている。ボアールは演劇の舞台を通して、演者と観客がダイアローグ(対話)を重ね、生活の中で直面している課題についてお互いが意識的になる場を設ける。その解決策を一緒に考え、それを舞台上で表現するのが被抑圧者の演劇である。
私もニューヨークに住んでいた頃に被抑圧者の演劇のワークショップに参加したことがある。そのワークショップでは、まるでコミュニティにおける実践が凝縮されたような感覚を得る。参加者は自分の身体を使って感情や考えを表現する。その表現の過程を通して「主体性」が育まれていくのである。ワークショップをファシリテートするのは、舞台裏の監督でも、頭巾をかぶった黒子でもない。演者自らが参加者とのダイアローグを通してその舞台を創り出し、自身も新たな意識化を経験するのである。
ワーカーにはその演者のような関与が求められる。コミュニティの活動では、身体も重要な要素であるが(例えば、会議での表情や会話する時のボディランゲージなど)、身体以上に言語が大きな意味をもつ。集会などでワーカーが発言する際に教科書どおりの「おきまりのセリフ」を並べてしまうと、一瞬でその舞台から人の心が離れていってしまう。
「住民の主体性が大切です。」
「この実践はまさに〇〇の機能と言えます。」
「皆さんの支え合いによって生活は守られています。」
心のこもっていない言葉の積み重ねによって、その実践からは魂が抜けていってしまう。残念なことに、魂の抜けたコミュニティを無理やり組織するために、地域のヒエラルキー構造やカリスマ性に依存する組織化(もはやそれは組織化とは呼べない)が展開されるのである。
今日もどこかで三文芝居が上演されている。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。