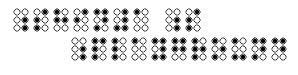掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第227号,2016年8月.
「実践の糧」vol. 30
室田信一(むろた しんいち)
近年、住民が事業の担い手となることを前提とした政府の政策が増えてきている。社会福祉の領域は国家予算に占めるその割合が大きいため、予算の抑制圧力が強く、結果として住民の関与を求める傾向はより顕著に表れている。介護保険制度の新しい総合事業と呼ばれる領域もその一つである。
新しい総合事業では生活支援コーディネーターと呼ばれる職員が全国に配置され、住民同士による支え合いの活動を各地で推進することが求められている。言い方を変えれば、それまで地域で支え合いの活動など取り組んでこなかった地域住民に「その気」になってもらい、生活支援のための活動を一緒に生み出していくことがその趣旨である。
「その気」になってもらう、というところが重要である。住民に「その気」になってもらうための存在を触媒と形容することがある。コミュニティ・オーガナイザーには触媒としての役割が求められると従来から言われている。触媒としての役割とは、潜在的な意識を表面化させることである。具体的には、大気汚染などの公害被害を受けながらもどのように意見表明をしていいかわからない住民の声を集めて、その声を政府や加害者に伝えるといった場合がある。その場合、住民が抱く潜在的な問題意識に働きかけることになる。一方、新たに開発された住宅地で、住民同士が交流する夏祭りのようなイベントを開催して親交を深めるというような場合もある。その場合は、住民の潜在的な交流意欲に働きかけることになる。何れにしても、住民に「その気」になってもらうために、コミュニティ・オーガナイザーは様々な方法を駆使する。
綺麗事を言ってしまえば、コミュニティ・オーガナイザーという触媒なしで住民が自ら立ち上がり、行動を起こすことが望ましい。しかし、組織化が自然発生する確率は低く、多くの場合お互いを牽制しあって誰も行動を起こさず、機を逸してしまうということが少なくない。したがって、第三者であるコミュニティ・オーガナイザーがその地域に関与することで、潜在的な意識を集めて、行動へと繋げるのである。
新しい総合事業に関していえば、今後、各地で事業が推進されるにつれ、住民に「その気」になってもらうための方法論が蓄積されていくことが期待される。その結果、住民の触媒としての生活支援コーディネーターの専門性が地域の中に浸透していくかもしれない。地域住民に効率よく「その気」になってもらうことが高い評価につながるようになる。その時に、生活支援コーディネーターはふと思うかもしれない。自分は何のために人に「その気」になってもらっているのだろうか、と。生活支援コーディネーターにとっての「大義」は何か、と。そこを見失ってしまうと、生活支援コーディネーターという仕事は精神的に消耗するものになるだろう。
私自身、ニューヨークでコミュニティ・オーガナイザーとして働いていた時にそのようなジレンマを抱いていた。次回はそのことについて書きたいと思う。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。