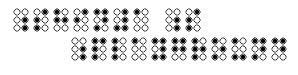掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第235号,2017年12月.
「実践の糧」vol. 38
室田信一(むろた しんいち)
私が、8年間のアメリカ滞在を経て、日本に帰国してから今年で12年目になる。帰国当初は慣れない日本文化の中で生活することに苦労した。渡米前の私は19歳だったため、大人としての経験が乏しかった。帰国した時は27歳だった。大人の日本人としての素養を全く身につけていないにも関わらず、周囲は大人としての振る舞いを私に期待した。
実はこの「振る舞いを期待する」ということは時に暴力的になる。
昨今、多様性への配慮であったり、ポリティカル・コレクトネス(政治的に正しい言葉づかいや振る舞い)を重視したりということが話題に上がることが多くなったと思う。それは、政治家の失言に代表されるように、配慮のない考え方や一方的な価値観を他者に押し付けてしまったり、社会の認識とのズレに気づくことのないままに自身の振る舞いを示してしまったりすることに端を発する。
しかし、その「配慮」や「ズレ」という捉え方自体が、顔のない集合体である「社会」や「世間」を意識したものである。結局は「世間」の価値観を前提に、その価値観が時代とともに変化したことから、各自が自身の価値観をその「世間」に合わせる必要がある、ということを求めていて、本質的には何も変わっていないのではないかと思う。
多様性に配慮することの重要性を指摘する人が、一方で礼節を強く求めるということもある。地域の現場ではそうした側面が顕著に現れる。そのため、ワーカーにはどのような態度で人に関わるべきかが問われることになる。表面では「福祉」の仕事をしていますという顔をしながら、そのワーカーが目の前の相談者に求める態度は偏った価値観で判断しているということがある。
人には誰しも価値観があり、その価値観をぬぐい去り、真っ白な状態になることはできない。政治学者のロールズが「正義論」の中で「無知のベール」という考え方を示している。それはまさに真っ白な状態になったと仮定して物事を判断することを意味している。政策論争をする際に真っ白な状態を想定して、検討することはできるかもしれないが、それが日々のワーカーの業務(特に面接業務)となると、その都度、真っ白な状態に切り替えるということをしていては追いつかない。そこでワーカーには自分の価値観に意識的になるという「自己覚知」が求められる。社会福祉の実践に身を置いている人にとっては当然のことだろう。
私が思っていることは、その自己覚知の結果が「世間」に近づくことになっている場合があり、そのことが最も恐ろしいということである。アメリカの公民権運動指導者のデュボイスは二重意識という考え方を示したことで知られている。アフリカ系アメリカ人であることで、アメリカ人としての意識とアフリカ系としての意識を持つことができ、その二つの視点からアメリカ社会や人間関係を見ることができると考えた。この二重意識はマイノリティのみに与えられる視点と考えられがちであるが、人種などの属性にかかわらず、自身の「ズレ」を通して世間を見ることの重要性を指摘していると捉えていいだろう。
そう考えると、みんなどこかズレているもので、私たちはそのズレた世界で生きていることに気づかされる。無論、ワーカーも含めて。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。