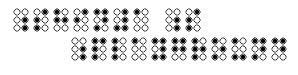掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第242号,2019年2月.
「実践の糧」vol. 45
室田信一(むろた しんいち)
ここ数年、私は本気で怒ることがなかった。社会福祉関係者や市民活動をしている仲間と雑談をしていて、何かに対して怒りを感じているという話を耳にすることがあるが、その度に、自分は同じレベルで怒ることができるのか不安になっていた。自分が冷めていることを残念に感じていた。というのも、社会を変えるエネルギーの根源として怒りの感情が重要だと思うからである。自分が理想と思う社会にとって、ある人の言動がその理想と逆行している場合に怒りを感じたり、自分が思う理想的な社会に対して矛盾している制度や仕組みがあると、それを何とかして変えてやるという怒りのエネルギーが湧き上がってきたりすると思う。自分にはそれが欠けているのではないかと、ここ数年、気になっていた。
確かに、現状に満足しているか、というと、やや満足しているところがあるように思う。私がずっと取り組んできたコミュニティ・オーガナイジングを理解して、それを実践したり、ノウハウを広めようと活動する仲間がいて、さらにコミュニティ・オーガナイジングを共に研究する仲間も増えてきた。そのように自分が考える理想的な状態に近づくことは幸せである。10年以上前、アメリカから日本に帰国したばかりの頃、誰もコミュニティ・オーガナイジングに耳を傾けてくれなくて「こんちくしょう!」と思っていた頃とは変わってしまったのかもしれない。
しかし、先日、人前で堂々と怒ることがあった。それは次のようなことを言われたことに起因する。「室田さんは本当にしんどい現場を知らない。」ここでいう「しんどい」とは過酷という意味で、過酷な思いをしている人たちが多くいる現場を私が知らない、とその人は言いたかったのである。私はその発言をした人物に対して、強く反発して、発言の撤回を求めた。「そうですかねぇ」とか「いや、そんなこともないですよ」と受け流すこともできただろうが、その日の私は違った。
実は、私が怒りを感じたのは、「しんどい現場を知らない」という指摘に対してではない。私が最も違和感を感じたのは、現場に対して「本当にしんどい」とか「しんどくない」という評価を下していることだった。その上で、より過酷な現場を知っていることが偉い、といった価値観を押し付けられたような気がした。
そもそも、私は現場に優劣をつけることが許せない。どのような現場も尊く、そこで行われている実践はどれも意味がある。よく見かける、誰にでもできる実践だとしても、その実践には文脈があり、思いがあり、意味がある。ちなみに、私はアメリカで不法滞在しながら家族をギリギリ支えている移民の人たちを多く支援していた。アフリカのモザンビークのスラムの開発支援に参加したこともある。それらの現場は「しんどい」現場かもしれないが、そこに優劣をつける意味はない。
大事なことは現場の優劣ではない。自分がその現場にどのように関わるかである。現場という人が生活する世界に足を踏み入れるのであれば、功罪含めてその影響に対して意識的である必要がある。生活者から遠く離れたところで、現場を評論するような物言いに対して怒ることができた自分を誇りに思う。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。