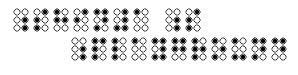掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第214号,2014年6月.
「実践の糧」vol. 17
室田信一(むろた しんいち)
「ケースワークは面接に始まり面接に終わる」という言葉があるらしいが、それになぞって考えるならば「コミュニティワークは会議に始まり会議に終わる」といえるだろう。多様な主体が一つのテーブルに集まり、議論を交わし、合意を形成して、計画を立て、資源を持ち寄り、行動に移していく。そうした協議の過程はコミュニティワークの根幹といえる。
しかし、その会議の進め方の技術や方法論はどれほど意識されているのだろうか。また、そのノウハウは蓄積されているのだろうか。個人的な見解に過ぎないが、多くの会議に参加する限りでは、あまり意識されていないように思う。
会議なんてどうやっても結果は同じと思われているのか、会議は形式的なもので、大きなトラブルなくやり過ごせばいいと思われているのか。とにかく、会議という場をとおして何かを生み出すということが意識された会議にはなかなか巡り会えない。
誰が司会を担当するのか、司会は持ち回りなのか、時間配分をどのようにするのか、発言する際は皆に同じだけの発言の機会が与えられるのか、誰が記録を取るのか、記録はどのように取られるのか、記録された内容はどのように共有され、承認されるのか、決議はどのようにおこなわれるのか、多数決か、全員が納得するまで話し合うのか、声の大きい人の意見がそのまま反映されるのか、そして、それらのルールはどのように決められるのか。
会議の進め方については何も議論されることがないままに、暗黙のルールを探り合いながら、会議が進んでいるということはないだろうか。
「ルールが明確でないこと」と「ルールがないこと」は同じではない。場には必ずルールがある。そして暗黙のルールは、その場にあらかじめ埋め込まれているものであり、多くの場合それは場の権力構造を反映している。参加者は、その暗黙のルールを受け入れることで、権力構造も受け入れるのである。
表向きは「参加者の主体性を重んじる」といっていても、会議の進め方が主体的な参加を認めにくい構造になっていたら、結局は会議の過程をとおして参加者は客体化されてしまう。では、どのようにすれば会議の文化を変えることができるのか。
残念ながら残された紙幅で説明できるほど単純なことではない。重要なことは一つ一つの手続きを曖昧にしないということである。「なんとなく」や「その場のノリ」で会議が進められることに、いつしか慣れてしまい、恒常化してしまうことで、疑問すら抱かなくなってしまう。
改めて会議を「科学」することが重要になる。詳しい内容は次号で書きたいと思う。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。