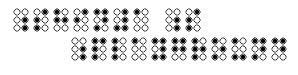掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第254号,2021年2月.
「実践の糧」vol. 57
室田信一(むろた しんいち)
私がアメリカ留学を決意したのは高校2年の正月だった。ニューヨークに住む親の知人が家に来たときに、アメリカに行きたかったらいつでも世話するよと言ってくれて、二つ返事で「行きたい」と言ったことを今でも覚えている。日本の大学に魅力を感じることができず、就職したいと漏らしていた私をみて、両親が知人を招いてくれたのかもしれない。しかし、高校3年になり、担任の先生に留学の希望を伝えると、日本の大学に進学してから考えろと頭ごなしに否定された。今でこそ高等教育のグローバル化が進み、海外の大学を目指すことは珍しくないが、今以上に人生のレールが固定化されていた当時、そのレールを外れることに対する反発は強かった。
俗にいう「出る杭を打つ」そうした日本人の価値意識は地域活動の中にも存在する。新しいことや既存の枠組みを外れることは容易には受け入れられない風土がある。市民活動界隈では近年「イノベーション」がキーワードになっているが、皮肉を込めて言えば、イノベーションのレールを敷こうとするそうした働きかけは、真にイノベーティブなものを除外しているように見えなくもない。真にイノベーティブなものはまさに出る杭のように少し目障りだったり、厄介な存在だったりするだろう。そのような存在だからこそゲームのルールを変えるようなイノベーションが起こせるのだ。
厄介な存在だからこそ、イノベーションを起こすことにはそれなりの痛みが伴う。私がかつて住んでいたニューヨークでは出る杭が打たれるという感覚を抱くことはなかった。その代わり、何か新しい取り組みをする際は、本当に魅力的で有意義な提案をしない限り人は集まらないし、1回目の集いに人が集まってもそこに参加する意義を感じなければ2回目の集まりに戻ってくる人はいない。義理や縁でとりあえず参加するという慣習はない。したがってオーガナイザー側は参加者一人一人の動機に対して敏感になる必要があるし、参加者が意見を反映できる余白を残さなければ、その企画は前に進まないだろう。
一方日本の地域活動では、声がかかった会議にとりあえず参加するし、一度参加したら継続して参加するという慣習がある。参加を取りやめることのハードルが高く、同時に一度始めた会を途中で解散することのハードルも高いように思う(失敗の烙印が押されて、次から声をかけづらいような空気ができてしまうからだろうか)。確かにそのような環境ではイノベーションが起こりにくいかもしれない。
そうした中、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、地域活動をめぐる力学が少し変わったように思う。何が起こるかわからない先行き不透明な状況においては、目的が曖昧であったとしても、つながっていることが重要な意味を持つ。災害時でも同様のことがいわれるが、コロナ禍でも同じ力学が働いているようだ。
「出る杭は打たれる」という話をすると、「出る杭」ばかりに注目してしまうが、そこにしっかりと埋まっている「出ない杭」があるからこそ「出る杭」の存在価値が際立つといえる。イノベーションも重要であるが、安定性・継続性が地域にもたらす価値を見つめ直すことも必要だろう。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。