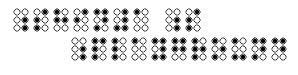掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第274号,2024年6月.
「実践の糧」vol. 74.5
室田信一(むろた しんいち)
話題の小説『成瀬は天下を取りにいく』と『成瀬は信じた道をいく』を読んだ。滋賀県大津市が舞台ということもあるので、関西在住の人にとっては身近に感じる内容が要所に盛り込まれている。物語は、さまざまなことにチャレンジを続ける女子高生成瀬あかりが、西武デパート大津店の閉店に際して、閉店を取り上げる地元のローカルテレビの生中継に毎日映り込み、西武への感謝を表明するという「アクション」から始まる。成瀬のそうしたちょっと変わった「アクション」が小説に登場する他のキャラクター(成瀬の友人など)の視点から描かれている。
この小説の読み方は人によってさまざまだろう。多くの読者は、成瀬の突拍子もない行動とそれを淡々と確実にこなす彼女の行動力に魅了されるのではないだろうか。ネタバレになるので詳細は書き控えるが、物語自体、成瀬の行動力に魅了される周囲の人間の模様を描くことで、成瀬の人物像を浮かび上がらせるという手法が用いられている。
この小説を読み進めると、読み手によっては成瀬がいわゆる「発達障害」の傾向があるということに気が付くかもしれない。「空気を読まない」成瀬の行動に周囲はひき、少し距離を置く。実際に小説の中では小学校5年生の時にクラスのみんなから無視されていたという記述がある。それでも当の成瀬は気にも止めず、まさに自分の信じた道をいくのである。
確かに成瀬は感情を表現することが苦手で、行動パターンの中に他者性が欠落しているという特性があり、いわゆる「発達障害」というカテゴリーで見られる(もしくはそうした診断が下る)ことはあるだろう。しかし私がそれ以上に感じたことは、成瀬を通して見えてくる日本社会の特徴である。小説を読み進めるうちに、周囲の空気を読まずに行動する成瀬の姿が、アメリカ人のようにも見えてきた。アメリカ人は、感情表現が豊かという点においては成瀬とは全く異なるものの、周囲の空気を読むことを是としない点において成瀬っぽいと思った。「アメリカ人」として一括りにすることはいささか乱暴ではあるものの、少なくとも私がアメリカから帰国した当初の自分に「成瀬っぽさ」があったのではないかと思う節が多々あり、成瀬の行動原理に共感すらした。
よく考えると、私がアメリカに留学した背景には、空気を読まなければならない日本社会の雰囲気があまりにも重く、そうした空気に敏感であり、過度に配慮してしまいそうになる自分をなんとか解放してあげたいという気持ちがあったことを思い出した。アメリカに住むと、知り合いがいないということ以上に、周囲の空気を読むことに執着しない関係性にすっかり心地良くなった。成瀬がアメリカに行くと、きっと普通に馴染むに違いない。小説を通して自分が日本社会の空気にまた押しつぶされそうになっていることに気がつくことができた。
この小説がよく売れている背景には、成瀬が空気を読まずに行動することへの爽快感があり、多くの読者が日本社会の閉塞感を感じていることを反映しているのではないだろうか。もしそうだとしたら、自分もまた「アメリカ人」に戻ってもいいのかもしれない。
※本原稿は「つなぐ」の掲載に間に合わなかったので、オンラインのみで掲載します。