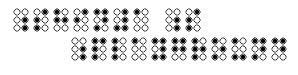掲載:『つなぐ』寝屋川市民たすけあいの会,第262号,2022年6月.
「実践の糧」vol. 65
室田信一(むろた しんいち)
先日、アメリカのブロードウェイミュージカル「レント」の来日公演を観劇してきた。演技の途中に急に歌を歌い出すミュージカルというものに、以前は馴染むことができず、関心がなかったが、「レント」が映画化された時に観てからミュージカルに興味をもつようになった。
「レント」は1990年代のニューヨークが舞台の物語である。低所得者が多く居住し、治安が悪いイースト・ヴィレッジというエリアのアパートに不法占拠して暮らす若者たちが登場する。彼らは貧困やエイズの問題に直面して、毎日を過ごすことに精一杯だけど、その一日一日を大切に生きる姿に胸が熱くなってくる。
私は高校卒業後に単身ニューヨークに留学した。当時はその動機についてうまく言語化することができなかったが、今振り返ってみると、大学進学や就職というレールがあらかじめ敷かれていて、そのレールに乗ることを強要される日本社会に違和感を感じていたのだと思う。自分の人生を生きているというよりも、社会によって生かされているという感覚が強く、何のために人生を生きているのかわからなくなっていた。
ところが、ニューヨークに行くと、そこには多種多様な人が生活していて、あらかじめ決められた人生のレールのようなものはなく、一人ひとりが自分の人生と向き合って精一杯生きているという雰囲気があった。私も、なぜニューヨークに来たのか、人生で何を達成しようとしているのか、何のために生きているのか、という問いを常に周囲から突きつけられるような感覚を得た。
しかし、人は弱い生き物で、そのように感覚を常に研ぎ澄まして生きていると徐々に疲れてしまう。疲れてきた時には休息が必要であるが、身体的な疲れよりも心の疲れの方が深刻だったりする。では、心の栄養をどこから得るかというと、同じように自分の人生と向き合っている仲間からである。人生にもがき苦しみ、だからこそ一日一日を大切に生きている仲間と出会い、彼らと想いを共有したり、苦しみを共有したり、希望を共有することで心が満たされていく。また、自分が辛くなった時に、仲間も同様にもがいているという事実が力を与えてくれる。
「レント」のストーリーの根幹はまさにそこにある。このミュージカルに登場する人物は皆「福祉的」な課題を抱えている。しかし自分の人生にオーナーシップをもって生きている。それに比べて、「福祉的」な課題は抱えていないものの、レールに乗っかって、社会の中で生かされている人生では、どちらが幸せなのだろうか。もちろん比較はできないし、人によってどちらを求めるのか分かれるだろう。
福祉の支援に携わると、どうしても「福祉的」なニーズを満たすことを重視してしまうが、「福祉的」な支援では満たすことができない側面にも光を当てることが重要だと、「レント」を観劇して改めて思った。
※掲載原稿と若干変更する場合があります。